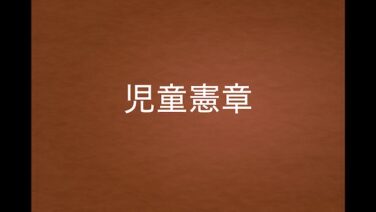 学び
学び 「児童憲章」とは?
最近、改めて「社会福祉」の勉強を復習しています。資格を取得した学生の時よりも、現在の社会情勢や自分の状況を踏まえての勉強となると、専門職以外の関連領域の学習が大切であることを実感させられます。今回は、「児童憲章」の内容が今の自分にとって大切...
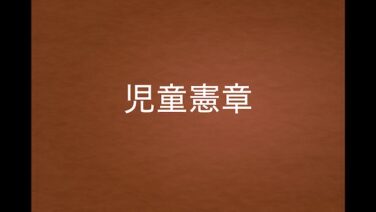 学び
学び  学び
学び 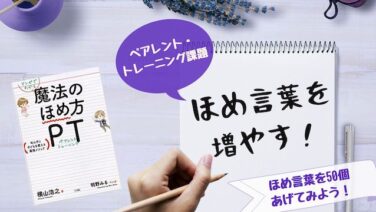 学び
学び 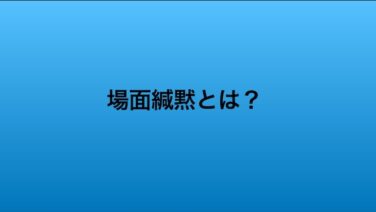 学び
学び  学び
学び 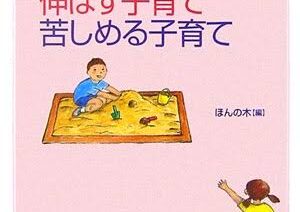 学び
学び 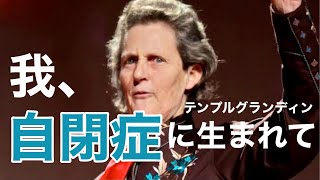 学び
学び  未分類
未分類 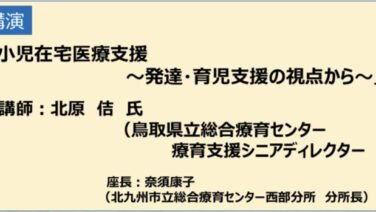 学び
学び 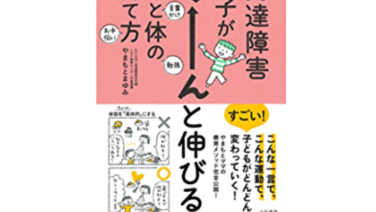 学び
学び