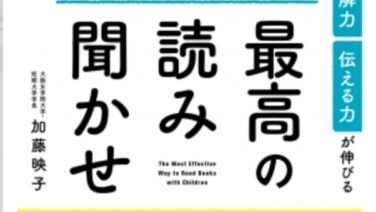 学び
学び 『言葉を引き出す読み聞かせ✨』
今回は「世界一受けたい授業」でも取り上げられた加藤映子著「最高の読み聞かせ」のご紹介です。 一般的に絵本の読み聞かせが良いと言われますが、どんな読み聞かせが言葉を引き出しやすいのか?と尋ねられると、「うーん…」と、返事に困ってしまう方もいら...
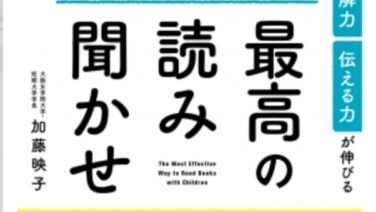 学び
学び 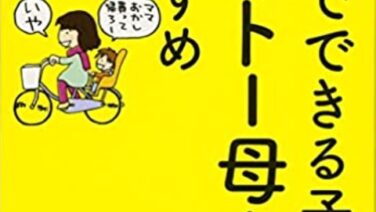 本の紹介
本の紹介 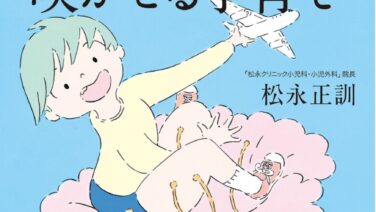 本の紹介
本の紹介 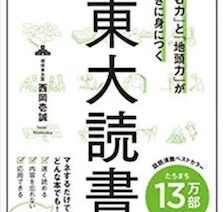 本の紹介
本の紹介  ICT関連
ICT関連  本の紹介
本の紹介  本の紹介
本の紹介 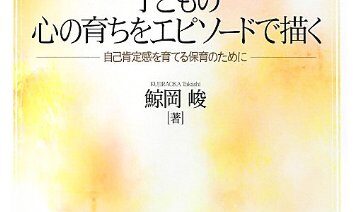 本の紹介
本の紹介  ICT関連
ICT関連  本の紹介
本の紹介