重い身体障害と重い知的障害を併せ持つ
障害児者を支援する施設「つばさ静岡」に
20年間勤務する浅野一恵先生の
講義を聞くことができました。
浅野先生は、2018年に
日本摂食嚥下リハ学会にて
『発達期」摂食嚥下障害児・者のための嚥下調整食分類2018』を
発表されています。
以下に、今回の気づきをまとめてみました。
「ストーリーを作り上げること」を意識して
これまで長らくの間、摂食・嚥下障害を有する
障害児に対応した嚥下調整分類は、
作成されておらず、
各施設での工夫と配慮に限られていました。
障害児にとって、安心・安全に
食べられる分類の作成を試み
策定・発表されたのが、浅野先生です。
普段のお仕事の合間に、中央の本部に
足繁く通い、各先生方と論議を重ね
試行錯誤してまとめあげた経緯も
お伺いする事ができました。
それら食事支援に掛けるエネルギーに
私は、脱帽しました。
講義の最中には、まとまりペーストや
まとまりマッシュの説明がなされ
お手軽で簡単な作成方法もご紹介頂きました。
ばらつきにくいまとまり感や
舌で押しつぶせる柔らかさ、
口腔内に残りづらい粘性など
様々な要因を考慮して作成していることもあり、
つばさ静岡の施設内に留まらず、
地域の特別支援学校にも広まってきている
現状もお知らせ頂きました。
安心安全に美味しく食べられるように
なったことで、食事介助の手間も減少し
何より、体調を崩す事が減った利用児者様の
報告を嬉しそうにお話されていたのが印象的でした。
そんな浅野先生は、
それぞれの利用児者様の
ストーリーを意識した生活のあり方を
語られていました。
安心・安全に美味しく摂取できる食事が
その人の生活の一部となり、
その人らしく居られる生活空間を
創造する事を目指しているように
受け取る事ができました!
さいごに
私は「食事は、家族の絆」という言葉に、
共感しました。
摂食・嚥下機能に、何も問題を持たない
私たちも、1日3回の食事に関する喜びは
計り知れないものがあることを
実感しています。
私は、妻でもあり母親でもあるので
基本的に、食事の準備を担っています。
1日の終わりを告げる最後の夕飯が
家族の好みとズレが生じると、
自宅の雰囲気も、ガラリと変わって
しまう事を知っているからです。💦
だからと言って、
毎日の夕食を豪華にしているわけでは
ありません。
家族にとっては、
それだけ、心と体を満たす場でも
あるのだなぁと感じているので、
心と時間にゆとりがある時は、
家族が喜ぶ食事を提供できたら…、と
考えている次第です。
そんな大切な食事場面を
摂食・嚥下機能に課題がある人とも
大切な時間を過ごせたなら
ずいぶんと幸せな時を過ごせるかも
しれないと感じました。
その為にも、今回お知らせ頂いた
貴重な情報を、職員や保護者様と
共有していきたいと思いました。
課題は、山積みですが、少しずつ
その山積みの課題を滑らかに
していけるように進みたいと思います。
浅野先生がまとめた
ご著書「こどもの伸びる力を信じる食事支援」
にもポイントがまとめられていますので、
ご興味・関心が有られる方は
ご覧になられてください!
今日も最後までお読み頂き
ありがとうございました。

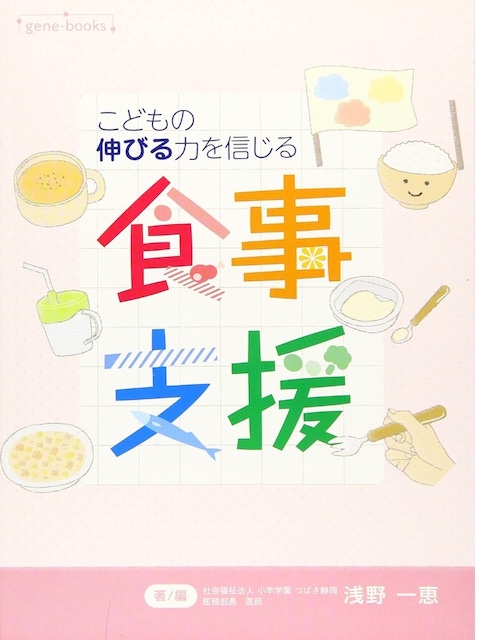


コメント