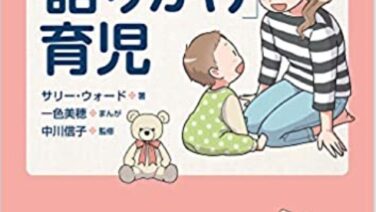 未分類
未分類 『ことばを育てたい方々へ』
今回は、イギリス人言語聴覚士のサリー・ウォードさんが、子どもの言語能力&知能を確実に伸ばす方法として提唱している「語りかけ育児」についてのご紹介です。「語りかけ育児」は画期的で分かりやすく、その効果も立証されており、イギリス政府も推奨してい...
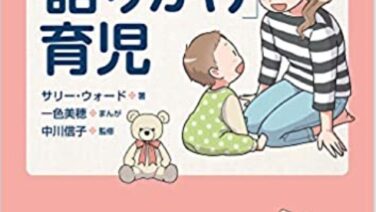 未分類
未分類 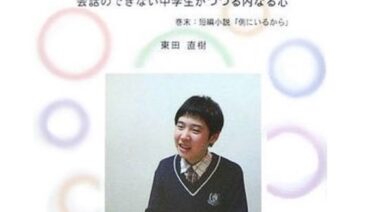 発達関連
発達関連 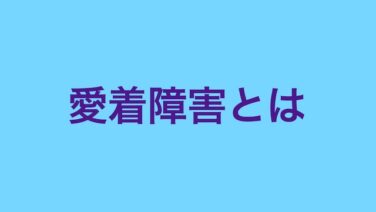 発達関連
発達関連  学び
学び  保育関連
保育関連 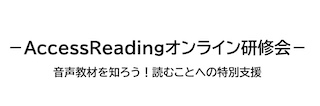 ICT関連
ICT関連 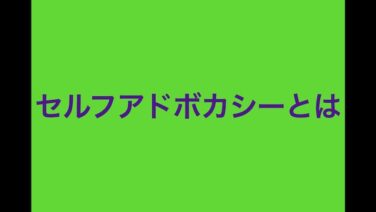 聴覚障碍
聴覚障碍  学び
学び  学び
学び  学び
学び