今回は、行動療法/ソーシャルスキル
マネジメント/構造化 という3つの
領域を学ばせていただいたので
1つずつの領域をまとめてみました。
行動療法
行動療法とは、全ての人間に共通する
行動の基本原理に基づき、子どもの
行動を理解し、問題行動を減らし、
適切な行動を増やす働きかけを言います。
行動療法には、
強化(ご褒美を与えて、行動を増やす)
例)子どもが良いことをしたら、褒める
消去(見て見ぬふりのことで、
良い行動も困る行動も、ご褒美を
与えずにいると、行動が減少します)
例)子どもが良いことをしても、褒めずにいると
その良いことをしなくなる
罰(行動の後に、不快な出来事があると行動が減少する)
例)事前に約束をしておいて、
危険で許し難い行動をした際に、
不快な出来事を起こすことで
行動の減少を進めます。
3つがあります。
*ご褒美を与えないと
やらなくなるのでは?との
質問がよくあるようですが、
まずは、安心して関われる
関係作りが大事なので、
褒めて安心・安全な信頼関係づくりを
しましょう。と言われます。
*罰に関して、極力使わない
方向で接することを言われます。
このペナルティが、効果的な対象は
発達年齢4歳以上と推奨されています。
未満児レベルの子どもに対しては、
ペナルティーを与えるのではなく
環境を整えることや
感覚特性を理解し対応すること
発達レベルに応じた関わりを
大切にして欲しいとのことでした。
ソーシャルスキル・マネージメント
ソーシャルスキル・マネージメントは、
社会生活や対人関係を育むために
必要とされる技能を育むことを言います。
認知に偏りがあり、情報をうまく
取り込めない事があり、
通常生活の中での誤った行動を修正し
やり方のコツを伝達します。
ただし‥、
療育場面のトレーニングで
うまく対応できるようになったとしても、
日常生活で応用して対応できるように
する事の限界も言われています。
子どもが本当にソーシャルスキルを
獲得したい場面(困っている場面)は
どのような場面であるのか?を
適切に把握することが大事です。
限界を言われるソーシャルスキルですが、
大人と安心・安全な信頼関係を
作るために、この方法は
有用であると言われていました。
構造化(環境支援)
構造化とは、自閉症及び
コミュニケーション課題を抱える
子ども向けの教育として
アメリカのノースカロライナ州から
広まっていった包括的プログラムです。
構造化された指導・支援として
1、場所の視点
2、時間の視点
3、活動の視点
4、視覚的手がかりの視点
をチェックし、環境面において
工夫・改善を図ることで、
子どもたちの生活のしやすさを
支援していきます。
ポイントは、
・一目瞭然で、見てすぐに理解できる提示
・コレが終わってから、コレをするよと見通しを
持たせること。
・雑な提示であっても、子どもが
わかりやすいが一番大事とのことでした。
口酸っぱく言われるのが
ヒューマンエラーではなく
システムエラーとして
捉えること。
誰かのせいと他人や自分を責めていると
前に進めなくなります。
馴染まない人にも
理解しやすい仕組み作りが肝です!
さいごに
今回の学びも、
自分の関わり方を「◯◯したい!」と
思える学びがたくさんで参考になりました!
中でも、今の私に響いた言葉は、
「他人を説得して変えようとか
注意や指示を出してコントロール
しようとかではなく、
子どもの人生が豊かとなる
支援内容を考えてサポートして欲しい」と。
その為にも、支援者はタフなメンタルが
必要。
思うようにいかない事は
沢山起こりますが、
それも学びや成長の為に、
必要な過程だと信じて、
毎日を、丁寧に生きたいと
思いました。
今日も、最後までお読み頂き
ありがとうございました!
〜こみゅばんばん〜

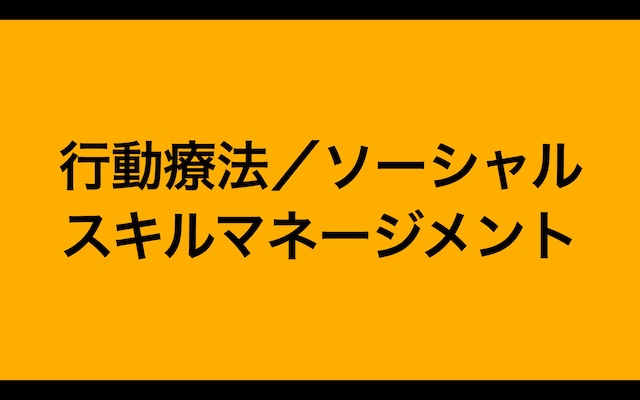
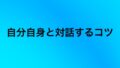

コメント